 |
||
| CIVICよろしくー |
RockzGoodsRoom > Outing > Outing2025 >
RockzGoodsRoom > Car >
| 以前から、仕事の夏休みは、お盆休みがないので交代制でとることになっている。 まだ1日、夏休みが残っていたので、9月30日は仕事の予定が何も入っていないのでとることにした。 当初は、全然行けていない、dakotaさんにハンバーガーを食べに行き、川上珈琲さんで、買えていないコーヒーの生豆を買って、家でローストしてのんびり過ごせたらと思っていたのだが、dakotaさんは月火休みだった・・・。 川上珈琲さんには行くとして、火曜が仕事休みのmisenさんも行くのだが、御影クラッセのPROFOODSで、最近はまっている製パンの道具を買いたいとのこと。 まぁ、御影クラッセに車停めるつもりでいたし。 あとは、御酒印帳のラベルを授かりに、灘五郷のひとつ、西郷の「沢の鶴資料館」にも行こうかな。 地図見ていると、兵庫県立美術館も沢の鶴から近いんだ。 兵庫県立美術館では「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s−1970s」というのを9月20日から開催しています。 面白そう。 学生の頃に近代建築の授業で出てきたようなのがいろいろと見られそう。 というわけで、神戸をうろうろしてみることにしました。 -07:30- ゆっくり目に目覚めます。 準備しながら、兵庫県立美術館のチケットをオンラインで購入しておきます。 ローチケでも、紙で出さなくてスマホで電子チケットでも行けるのがありました。 どんどんペーパーレスだなぁ。便利だけど、文化的なチケットって、チケット自体が思い出の一部になったりもするので、いろいろと複雑ですな。 -09:15- では行きますか。 |
 |
||
| CIVICよろしくー |
| 県道336号を南下します。 |
 |
||
| ぽっかり雲が浮かんでいる |
| R171に出て、さらに南下。 |
 |
||
| HondaCars兵庫 |
| R2を西へ走ります。 |
 |
||
| R2とR171の交差点 |
| ずんずん走っていきます。 -09:55- 「御影クラッセ」にやってきました。 |
 |
||
| 駐車場に入れます |
| 車を停めて、入るとちょうど10時。 開店です。 まずは1階の「PROFOODS」へ。 |
 |
||
| PROFOODS |
| 製菓・製パン材料及び関連器具のお店ですが、母体は岡山に本社を置く「ヒラタ」って製菓・製パン用原材料、包装・衛生資材、食品機器・店舗厨房設備の販売の会社だそうです。 最近、バゲット作りにはまるmisenさんが、いろいろと欲しいものがあるそうです。 というわけで、いろいろと購入。 ちょっと、3階のセリアも寄ってみたり。 さて、川上珈琲さんは11時からですが、御影クラッセの中で昼食を早い目に食べてから伺いましょうか。 3階の飲食店は11時からのようですが、2階のクラッセカフェに面した店舗は10時からやっているようですね。 -10:45- というわけで、久々に、モスバーガーで食べることにしました。 メンチカツチーズバーガーをセットで。 |
 |
 |
|
| できあがりを待ちます | モスとペッパーランチが並ぶ |
| ページャーが鳴り、取りに行きました。 |
 |
||
| ひさびさのモス |
| 混まないうちにいただきました。 では、「川上珈琲」さんに向かいますか。 一旦、御影クラッセを出ます。 |
 |
||
| 阪神・御影駅 |
| てくてく歩いて行きますよ。 -11:10- 「川上珈琲」さんにやってきました。 |
 |
||
| 入られる先客さんかな? |
| 店前におられた女性は結局入られませんでした。 お久しぶりですー。 いつものように、試飲させてもらいます。 あ、試飲のコーヒー、温かい。 開店すぐは、試飲用コーヒーも淹れたてなので、お勧めとのこと。 |
 |
 |
|
| 試飲コーヒー | 温かいです |
| 試飲の結果、季節のコーヒーをホットでいただこう。 |
 |
||
| FUJI ROYALの焙煎機 |
| 淹れていただいたコーヒーを飲みます。 美味しいなぁ。 |
 |
||
| 川上珈琲のカップ |
| 生豆もいただいていきますよ。 今回は ・エチオピア イルガチェフェ ナチュラル ・コロンビア ボンボ農協 ウォッシュド ・インドネシア マンデリン それぞれ300gずついただきました。 |
 |
||
| カウンター |
| 100g(weroastで50g×2回)の焙煎で、各種3回分ってところ。 2か月くらいは楽しめるかな。 焙煎した豆は20日間くらいで飲みきるのが良いと聞いたことがあるけど。という話をしていると、あながちそうでもないそうです。 焙煎して早い目に飲むのが美味しい場合もあるし、 焙煎したてはガスが出るので数日置いておいたほうがいいのは確かですが、日数によって味が変わるのも、だいぶん置いておいたふがいいというのもあるそうで、川上さんは焙煎した豆を販売する時は、すぐに飲むか、しばらくしてから飲むかで、提供するものも合わせているとのことでした。 細やかな気配りですね。 生豆だと1年は保存しておけるので、焙煎した豆を大量にストックするよりは、300g程度を都度焙煎して使うのが一番よさそうという結論に自分の中では出ています。 生豆も値段上がってきているのでしょうかねという話になり、原産国での不作や、輸送コスト上昇などに加え、中国国民の嗜好の変化でコーヒーが中国に流れていることもあって、1割くらいは上がってきているとのこと。 なので、これまでは少量入荷だったのを、ある程度まとめた量を入荷して、その分で割り引いてもらうなどの対策をしているとのことでした。 ちなみに、川上珈琲さんの場合は、豆売りは元値に対応せざるを得ないところはあるけど、淹れている分には、ほぼ価格を上げていないとのことでした。 ステキ。 今、世界的に船舶の空きコンテナが不足しているそうです。 コロナ禍から巣ごもり需要が増えさらに感染拡大で港湾作業員が不足したこと、その後紛争などで航路変更を余儀なくされ、移動距離が長くなることで、洋上に滞在するコンテナの数が増え、空きコンテナが足らないことから取り合いで価格高騰が続いているそうです。 いろいろと難しいですね。 |
 |
||
| ひがしなだスイーツめぐり? |
10月4日〜11月9日の期間で、「神戸ひがしなだスイーツめぐり」ってのをやるようです。 これですな。 川上珈琲さんも参加されています。ティラミス出されるようですね。 ありがとうございましたー。 また来ます。 御影クラッセに戻り、では行きますか。 |
 |
||
| 阪神電車 |
| 弓場線を南下し、R43に出ます。 |
 |
||
| 阪神高速の下を走る |
| 都賀川沿いに、都賀川右岸線を南下していきます。 |
 |
||
| 都賀川大橋 |
| -12:05- 「沢の鶴資料館」にやってきました。 駐車場はミュージアムショップに隣接していますが、資料館に行くには一旦敷地から出て歩いて行きます。 |
 |
||
| 見学コース |
| お向かいは樽屋さんですかね。 「たるや竹十・西北商店」と言うらしいです。 |
 |
||
| 外で作っているのかなぁ |
| 資料館の南側を歩いて行きます。 |
 |
||
| 風情があるね |
| では、「沢の鶴資料館」を見学しましょう。 |
 |
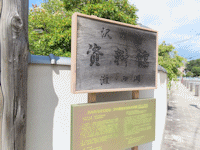 |
|
| 外からながめる | 兵庫県指定文化財 |
| この資料館は江戸時代末期に建造され170年以上の歳月を経てきたと考えられる大石蔵です。 酒造りの文化を広め、後世に伝えることを願って資料館として公開されています。 |
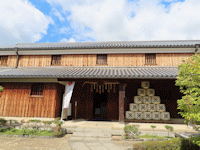 |
||
| 資料館 |
| 井戸がありますね。 仕込水とは違うのかな。 |
 |
 |
|
| 井戸 | ※印の樽 |
| 「沢の鶴」は、1717年(享保2年)に創業。その当時は両替商で大名蔵屋敷に出入りし屋号を「米屋」として藩米を取り扱う仕事を行っていました。 商標が※印なのは、その別家の米屋喜兵衛が副業で酒を造り始めたためとのこと。 1898年(明治31年)石崎合資会社に改組、株式会社後1964年(昭和39年)沢の鶴になりました。 関西人にはTVCMでの「さわ〜のつる〜♪」というのが耳に残っていると思いますね。 ちなみに、「沢の鶴」の公式Xは「沢の鶴【公式】♪さわぁ〜の つぅ〜る♪」 (@sawanotsuru1717)となっています(笑) 灘五郷の内の、西郷にある酒蔵になります。 この資料館は、1978年(昭和53年)に全国で初めての酒蔵の公開資料館としてオープンしましたが、1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災で倒壊してしまいます。 1999年(平成11年)に全国初の木造免震構造を採用し再建しています。 兵庫県有形民俗文化財に指定されており、近代化産業遺産にもなっています。 ちなみに、「沢の鶴」は、1993年(平成5年)に、これまではっきりしていなかった日本酒の冷・燗における温度の定義を研究発表しました。 これは、沢の鶴では日本酒と料理の相性研究会というものがあり、日々自分自身の色と日本酒がどのように繋がる可能性があるのかを研究していて、そちらで発表されたものです。 資料館は無料で見学ができますが、係の方がおられました。 資料動画が見られるそうで、係の方にお願いすると流してもらえます。 |
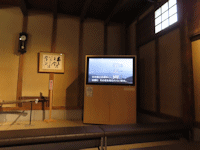 |
||
| 動画を観ます |
| 「沢の鶴」は、1885年(明治18年)に「澤之鶴」を商標登録しました。以後、1991年(平成3年)に「沢の鶴」に変更するまでの106年間は澤之鶴だったのですね。 沢の鶴(澤之鶴)は、「太陽の神・天照大神を伊勢にお祀りしたとき、伊雑の沢で頻りに鳥の鳴く声が聞こえたので、いぶかしく思った倭姫命がその啼き声の主をたずねたところ、真っ白な鶴がたわわに実った稲穂をくわえながら鳴いているのを見つけた。鳥ですら田を作って大神へ神饌を奉るのかと深く慈しんだ倭姫命は、伊佐波登美神に命じてその稲穂から酒を醸させ、初めて大神に供え奉るとともに、その鶴を大歳神(五穀の神)と呼んで大切にした…」という伊雑の宮(伊勢内宮と同じ地位を許されている別宮)の縁起が元になっているそうです。 |
 |
||
| 澤之鶴 |
| 昔ながらの酒造りの動画を拝見して、昔ながらの酒造りの工程に沿って見学します。 |
 |
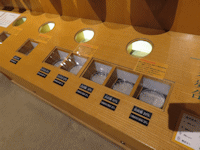 |
|
| 稲穂がある 山田錦はでかいですね |
精米歩合 |
| 地下構造の「槽場」跡があります。 |
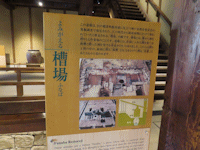 |
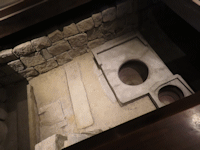 |
|
| 解説 | 槽場跡 |
| 全国でも珍しいとされる遺構で、槽場とは醪から酒を搾りとる作業場のことです。 1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災により資料館建物は全壊しましたが、復旧・復興に取り組む中で発見されたのが1839年(天保10年)と記された棟梁による墨書や、発掘作業により発見された槽場でした。 震災がなければ埋もれたままの遺構だったのかもしれません。 「釜」の、洗米や蒸米のコーナーです。 |
 |
||
| 昔は薪釜ですよね |
| 大釜の直径は1.5mあるそうですよ。 |
 |
 |
 |
| でかい | 脇釜 | まんじゅう 落し蓋のことかな |
 |
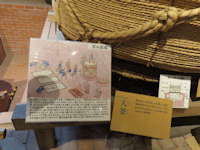 |
 |
| いいねー | 大釜の解説 | 道具いろいろ |
| 灘五郷のある阪神間は、六甲山系と瀬戸内海に挟まれた地域で、精米に関しては六甲山系から流れる川の水を利用して水車精米が行われていました。 |
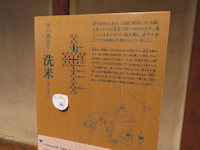 |
||
| 洗米 |
| 洗米は、平桶に入れた米を足洗でするんですね。 足洗は機械化されていない時代には、普通にされていた工程です。 冬期の厳しい寒さの中では重労働だったのでしょうね。 平桶に水を入れ、はじめに70回足踏みしてすすぎ、次いで一呼吸入れてから50回、最後に30回踏んで仕上げるのを、七五三と言ったそうです。 |
 |
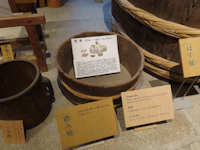 |
|
| 洗米して漬桶で浸漬します | 七五三の洗米 |
| 埋蔵文化財調査の出土品とかもあります。 |
 |
 |
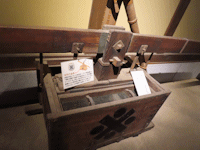 |
| 安土桃山時代の備前焼の大甕 | 人力消火ポンプ | 1860年(安政7年)の消火ポンプ |
| 「醪」の醪仕込みコーナーです。 |
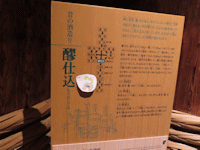 |
 |
|
| 解説 | 仕込用桶 |
| 甑の底、中央噴気口の蓋として上記を均等に分散させる用具の「猿」というのがありました。 |
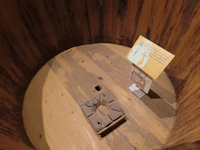 |
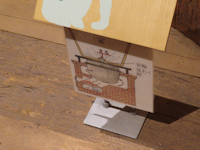 |
|
| 猿です | 解説 |
| 寒造りで仕込んだ新酒を火入れし、大桶に入れてひやおろしのシーズンの秋まで寝かせますが、その際に雑菌が入らないよう、和紙で目張りをして密封していたそうです。 |
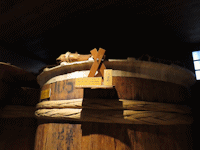 |
 |
|
| 目張りの際に使う「つばめ」って器具 | 解説 |
| 酒造りには独特の用具が多いですね。 |
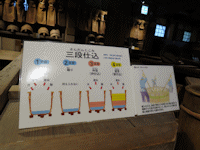 |
||
| 三段仕込みの解説 |
| 「搾」の上槽のコーナーです。 |
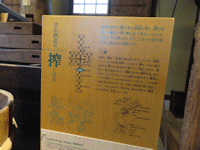 |
||
| 搾り |
| 醪を出す時に、大桶からじょうごを使って出します。 |
 |
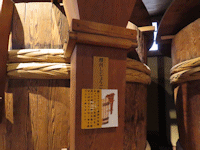 |
 |
| 醪出しじょうご | 解説 | 効率性と無駄の省きですね |
| 舟搾りの槽があります。 |
 |
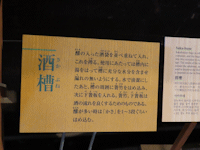 |
|
| 舟搾りです | 解説 |
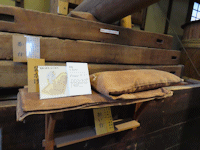 |
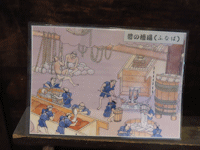 |
|
| 醪を入れる渋袋(しぶくろ) | 昔の槽場 |
| 搾った原酒は白濁しているので、大桶に入れ放置して、滓が沈殿するのを待ちます。 |
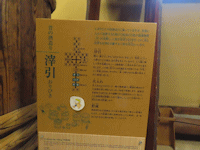 |
 |
|
| 滓引き | 上の栓から抜くと滓なしの原酒が出せます |
| いろいろ道具がありますね。 |
 |
 |
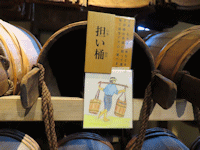 |
| すえがき どうがき | 担い桶や渋袋 | 解説 |
 |
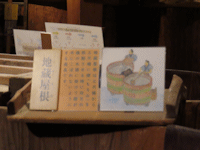 |
 |
| 大桶から出す時に担い桶を置く台 | 大桶から大桶に移動させる時に桶外にこぼさないようにする地蔵屋根 | 杓もいろいろな種類があります |
| 水は、西宮の宮水を船で運んでいました。 |
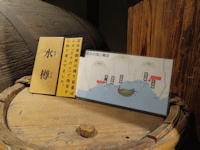 |
 |
|
| そうなんだ | だかい水樽 |
| 2階への階段のところに、杜氏の解説がありました。 以前にも書いたことがありますが、杜氏は、蔵元とは異なる、請負業となっていました。 杜氏は蔵元からその年の酒造りを全責任を任されて請け負います。 配下にどういう蔵人を従えるかに関して杜氏は全面的な権力と責任を持ち、蔵元は口をはさみません。よって、蔵元と杜氏の間、杜氏と蔵人たちの間には、まったく別の労使契約が交わされていたことになります。 杜氏は、その技術により一つの流派を形成し、杜氏集団を結成し、奥義を持っています。 当然ながらそういう情報は、流派から外へ伝授することは許されていない。というのが昔からのセオリー。 灘五郷の場合は、丹波篠山からの丹波杜氏が伝統的に酒造りをしてきました。 夏の間は農業を営み、秋の稲刈りが終わると杜氏は自分の村の若い者や、近隣で腕に覚えのある者に声をかけて、その冬のための酒造り集団を結成します。 |
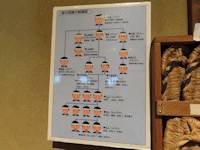 |
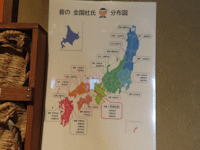 |
|
| 杜氏を頂点とした蔵人集団 | いろいろな杜氏集団 |
| 日本酒造りは、江戸初期までは四季醸造と名づけられる、新酒、間酒(あいしゅ)、寒前酒(かんまえざけ/かんまえさけ)、寒酒(かんしゅ)、春酒(はるざけ)と年に5回、四季を通じて酒が造られていましたが、1667年(寛文7年)、当時もっとも酒造技術が進んでいた兵庫・伊丹でそれまでの寒酒の仕込み方を改良し、寒造りの技法が確立しました。 1673年(延宝元年)、徳川幕府は酒造統制の一環として寒造り以外の醸造が禁止することになりました。 概して土地が乏しく夏場の耕作だけでは貧しかった地方の農民が、農閑期である冬に副収入を得るべく、配下に村の若者などを従えて、良い水が取れ酒造りを行なっている地域、いわゆる酒どころへ集団出稼ぎに行ったのが始まりですが、一方で幕府の酒造統制は、農閑期の冬期のみに酒造りを限定させることにより、春から秋は農業に専念させられるという考えもあったようです。 宝暦の大豊作で米相場が下落したことにより、米の消費のため1754年(宝暦4年)の勝手造り令により、酒は自由に造れるようになり、農村からの出稼ぎが増え、杜氏集団が各地に形成されていきます。 特に、北陸や東北地方の諸藩では、領民の貧窮を救済するために、摂泉十二郷や灘五郷など酒造りの先進地域から杜氏などを招聘(ヘッドハンティング)し、そこに地元の農民を入れて技術を習得させるといった手法がとられました。 岩手の南部杜氏はこのようなパターンで生まれたそうです。 ただ、灘酒の生産量増大により、人材流出、頭脳流出を防ぐためにも、天保年間(1830〜1844年)には灘の蔵元はほとんど丹波杜氏で占められるようになっていたそうです。 杜氏になるには、飯焚から始め、全工程に習熟するまで数十年を要しましたが、その仕事の内容にふさわしい敬意を払われ、収入面でも恵まれ、「杜氏になれば御殿が建つ」などと言われたそうです。 2階に上がります。 「もと(酒へんに元)」の「もと仕込み」コーナーです。 |
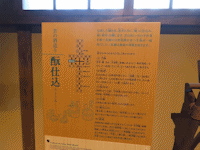 |
||
| 解説 |
| 「一麹、二もと、三造り」と言われるように、もと(酒母)造りは二番目に重要な工程です。 |
 |
 |
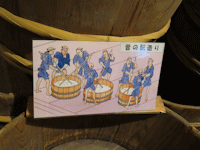 |
| もと卸桶 | もと造りに使った半切桶 | 昔のもと造り |
| 道具の名前にも「さる」、「つばめ」、「うぐいす」、「ハト」、「キツネ」、「かえる」とか動物の名前が付いたものも多くあります。 |
 |
||
| 細かい道具いろいろ |
| 樽廻船の大きな模型があります。 |
 |
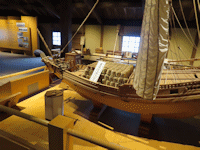 |
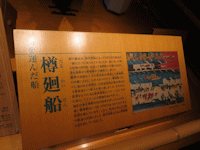 |
| 江戸への下り酒を運ぶ | 樽いっぱい | 解説 |
| 西郷の昔の模型がありました。 |
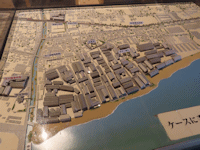 |
||
| 今や酒蔵は沢の鶴だけ |
| 沢の鶴の年表がありました。 |
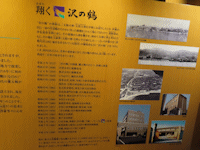 |
||
| 300年の歴史です |
| 千葉県市川市にも沢の鶴の会社があったそうですね。 |
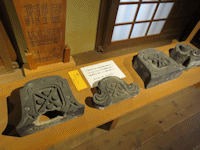 |
||
| 明治時代のその鬼瓦 |
| 菱垣廻船と北前千石船の模型がありますね。 |
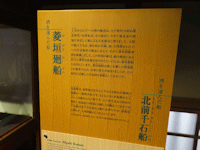 |
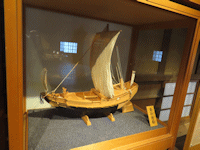 |
 |
| 解説 | 菱垣廻船 | 北前千石船 |
| 樽廻船と菱垣廻船どちらも江戸時代に上方(大阪)と江戸(東京)を結んだ海上輸送船でした。 菱垣廻船は、1619年(元和5年)に和泉国堺の商人が紀州の富田浦の廻船を雇って江戸へ回航させたのが始まりで、多種多様な日常の生活物資を運んでいました。 樽廻船は、1730年(享保15年)、菱垣廻船問屋に属していた酒問屋が、菱垣廻船の使用を停止し新たに酒を主な荷物とする樽廻船での輸送を開始したことが始まりです。 菱垣廻船が酒以外の様々な日用品や食料品などを輸送したのに対し、樽廻船は酒樽を専門に輸送する船として登場し、輸送の合理化によって菱垣廻船を圧倒するほどの速さと効率を誇ったそうです。 菱垣廻船のほうが輸送力のある大型船ですが、樽廻船は酒樽輸送に特化した船として出てきましたが、そのうち早く着くほうがいいということで、樽廻船が次第に主流になったそうです。 樽廻船と菱垣廻船は上方(大阪)から江戸(東京)へのルートですが、北前船は日本海を運ぶ、西廻り航路です。 樽廻船と菱垣廻船は運ぶのが主流でしたが、北前船は運ぶことに加えて、東北や北海道にまで足を延ばし、現地での買い付けを行いその荷を積み戻るといったこともしていました。 |
 |
||
| いろいろな古い道具 |
| 昔の広告や酒ラベルもありますね。 |
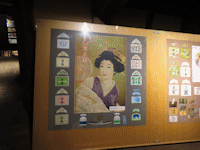 |
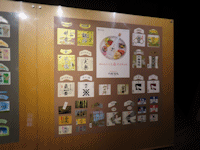 |
|
| 昭和初期のポスター | ラベルいろいろ |
| 「麹」の麹づくりコーナーです。 |
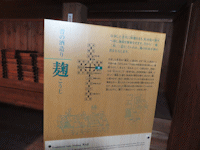 |
||
| 麹ですよ |
| 麹室を見学できます。 |
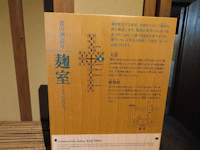 |
 |
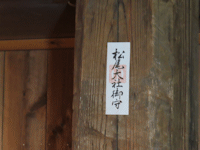 |
| 解説 | 麹室です | 松尾大社のお札 |
| 酒樽つくりも展示がありました。 |
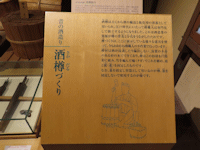 |
 |
|
| 解説 | 材料いろいろ |
| てことで、資料館の見学は終了です。 |
 |
||
| 2階から屋外階段で降りる |
| 降りたところにはお社がありました。 |
 |
||
| お社 |
| そしてミュージアムショップへ。 |
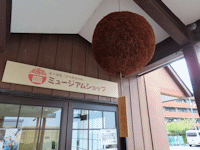 |
||
| 酒林 |
| 試飲は、蔵限定原酒と梅酒が味わえます。 misensさんに試飲してもらいますよ。 |
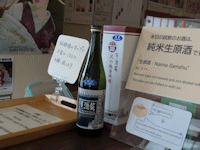 |
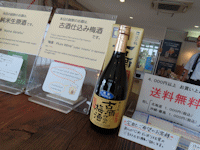 |
|
| 澤之鶴純米原酒 | 沢の鶴古酒仕込み梅酒 |
| 蔵限定原酒は18度あります。 梅酒は古酒で漬けているそうです。 古酒も年代によって何種類かあるそうです。 「お高いんでしょうね?」と聞いてみると、30年物の古酒がありますが、ウイスキーの30年物よりははるかに安いですよとのこと。 そうだよねー。 30年物のウイスキーって100万円くらいするもんね。 |
 |
||
| 1991 1997 2008 2010 |
| 今でこそ、日本酒=清酒で透明度が命で色がついているのは古いのか?と言われたりもしますが、本来の日本酒は、うっすらと黄色がかっているもので、透明なものは炭などで脱色している場合が多いです。 しかし、古来より日本酒を熟成させたものも存在しており、江戸時代には5〜10年寝かせた熟成古酒が造られ、九年酒を主力商品とする大和屋又(大和屋又左衛門)では、新酒の3倍の値段で売られていたとの記録もあります。 ということで、ヴィンテージ古酒(熟成種)の年代違いのセットがあったので買ってみよう。 結局、試飲した蔵限定原酒と古酒仕込み梅酒、熟成種をお買い上げ。 |
 |
||
| 明日は日本酒の日ですよ |
| あ、御酒印帳持っていますとラベルもいただきました。 ありがとうございますー。 出る時にはちょうど観光バスがやってきました。 勧告の観光ツアーご一同様のようでしたね。 さて、市道を走り、国魂線から浜手の道路を西へ。 |
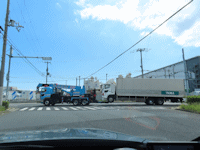 |
||
| 大型トラックが運ばれていた |
| 灘浜脇浜線に入ります。 |
 |
||
| ミカエル |
| -12:55- 「兵庫県立美術館」にやってきました。 |
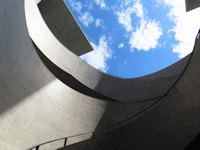 |
 |
|
| 駐車場からの吹き抜け | キラリ |
| 駐車場割引を受けて、入館券はローチケの電子チケットがあるので3階の企画展示室へ。 「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s−1970s」は、国立新美術館からの巡回展となっています。 |
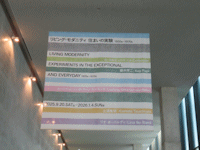 |
 |
|
| これ観ます | 電子チケット |
| 3階にやってきました。 |
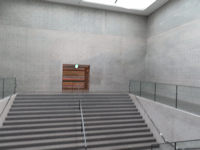 |
||
| あの奥から入ります |
展覧会の概要としては(美術館HPより)
傑作14邸を中心に、20世紀の建築家たちの挑戦を7つの観点に着目して紹介しています。 |
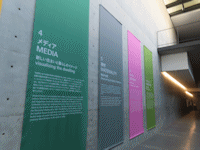 |
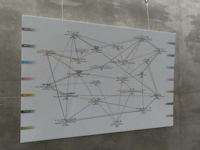 |
|
| 7つの観点 | 14邸と7つの観点の繋がり |
| ・衛生 : 清潔さという文化 ・素材 : 機能の発見 ・窓 : 内と外をつなぐ ・キッチン : 現代のかまど ・調度 : 心地よさの創造 ・メディア : 暮らしのイメージ ・ランドスケープ : 住まいと自然 てことです。 案内図とガイドブックを観ながらいざ鑑賞。 |
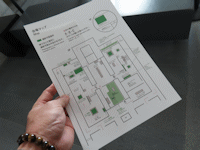 |
||
| 案内図 |
| 撮っていい場所とだめな場所があります。 まずは・・・ ●ル・コルビュジエ「ヴィラ・ル・ラク」です。 1923年建築。 スイスのレマン湖畔に、ル・コルビュジエが両親のために建てた小さな住宅です。 ほどなく母ひとりが住むようになったそうですが、湖に面した11mの長い窓が特徴の細長いコンパクトな空間には、来客時のベッドも含めて、必要最小限の設備が機能的におさめられています。 展覧会では 窓辺を再現した空間が広がります。 |
 |
 |
|
| 実物大の窓 | 長い窓のおうち・・・でかいな |
| 兵庫県立美術館は、安藤忠雄設計ですが、安藤忠雄が敬愛する建築家がル・コルビュジエです。 そういえば、愛犬にコルビュジエって名付けていたって話もあったなぁ。 ●藤井厚二「聴竹居」です。 1928年建築 |
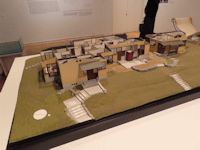 |
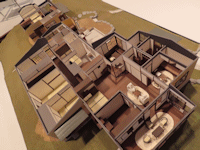 |
|
| 聴竹居の模型 | 大邸宅だな |
| 藤井厚二デザインの椅子などもあります。 |
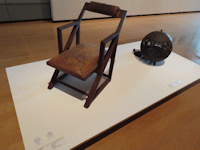 |
||
| 枕付肘掛け椅子と青海波暖房器具 |
| 京都の大山崎町の山林に建つ、藤井厚二の5番目の自邸です。 家族と暮らした「本屋」、趣味を探求した「閑室」、来客を招いた「茶室(下閑室)」からなります。 木造モダニズムの傑作と称されますが、日本の気候風土や生活様式を意識した工夫が凝らされていまする。 聴竹居の写真が飾られていました。 |
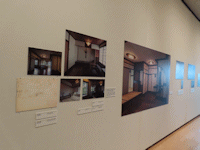 |
 |
 |
| 和モダンな感じ | いいねー | 緑と紅 |
| 水平連想窓という発送は、当時の建築には斬新でした。 ●ミース・ファン・デル・ローエ「トゥーゲントハット邸」 1930年建築 こちらは撮れる資料はありませんでした。 チェコ共和国ブルノ市にある、繊維業で成功したトゥーゲントハット夫妻の邸宅です。 通りから見ると平屋のようですが、高台の地形を生かした3階建ての建物です。 内部には、ミース・ファン・デル・ローエがデザインした家具が置かれました。 鉄の独立柱で支えられた空間は、カーテンやオニキスの間仕切りなどで、機能的に緩やかに区切られています。 大きなガラス窓は、機械式で上げ下げされるものですが、1930年にこのようなアイデアがあったのですね。 動画があり、結構面白かったです。 続いて暗室がありました。 ●ピエール・シャロー「メゾン・ド・ヴェール」 1932年建築 パリの婦人科医のクリニック兼住居として設計されました。 元々別の居住者がいた3階建ての建物だったのですが、3階の入居者が移転を拒否したため最上階である3階を鉄骨で支えつつ、下2層を解体して3フロアが新設されました。 ガラスブロックのファサードで覆われた内部は、グリッド状に仕切られ、窓や棚、扉などには、機械仕掛けのさまざまな可動システムが導入されています。 暗室では、CT検査のように輪切り画像が出て、パートパートで動画が再生され使い勝手がわかるようになっていました。 |
 |
||
| ピエール・シャローデザインの書斎机 椅子 フロアースタンド |
| ●土浦亀城「土浦亀城邸」 1935年建築 こちらは撮れる資料がありませんでした。 土浦夫妻による2つ目の自邸です。 東京の上大崎に建てられた鉄骨造の建て方を流用した木造乾式構造の建物は、様式、整備ともに欧米の最新の動向を取り入れつつ、日本の風土にも適合するよう設計されました。 内部は、敷地の高低差を生かした5つのフロアでゆるやかに繋げられています。 妻の土浦信子は、家事労働の軽減を意図して台所を機能的に設計しています。 ●アルヴァ・アアルト「ムーラッツァロの実験住宅」 1954年建築 |
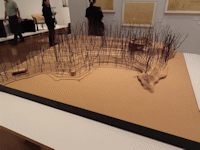 |
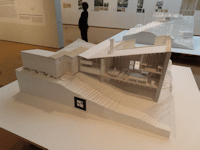 |
|
| 全景模型 | 材料の質感はわからないね |
| フィンランドのパイエンネ湖にある小さな島、ムーラッツァロ島に建てられた、夏を過ごすための自邸です。 入江から伸びた小道の先のレンガやタイルで覆われた中庭のある本住宅は、敷地内のサウナ小屋や船着場とともにデザインされました。 自然との調和や共生を目指したアアルトの思想が実験住宅という名の通りいろいろなアイデアが試されています。 ●広瀬鎌二「SH-1」 1953年建築 こちらは撮れる資料はありませんでした。 広瀬鎌二がSH-72まで手がけた鉄骨造りの「SHシリーズ」の記念すべき第一作です。 1953年に鎌倉材木座に建てられたこの自邸は、極限まで細くした鉄骨のほか、ガラス、レンガ、コンクリートなどの工業製品を材料とした、極めて実験的な住宅でした。 ●リナ・ボ・バルディ「カサ・デ・ヴィドロ」 1951年建築 |
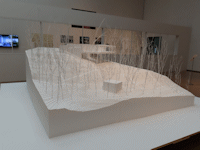 |
||
| 全景模型 |
| イタリア出身のボ・バルディが、ブラジル国籍を得た1951年にサンパウロに建てた自邸です。 高台のガラスファサードで覆われた建物の周囲には、ボ・バルディ自身が吟味して植物を植えました。 植物や土着の文化に関心が高いボ・バルディは、その開放的な室内を、地元の木材を使って自ら制作した家具や、アートディーラーの夫とともに集めた美術品や民芸品で満たしました。 ●ジャン・プルーヴェ「ナンシーの家」 1954年建築 |
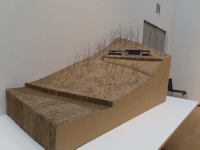 |
 |
|
| 自分で作った家 | でも結構よさげ |
| エンジニアだったプルーヴェが、自身が経営していた工場で余っていた部材を用いて組み建てた自邸です。 プルーヴェは建築家ではありませんでしたが、構想段階からの変更を余儀なくされながら、プルーヴェ自身が設計、施工までも手がけました。 傾斜地に最小限の平地を整え、ありあわせの部材を組み合わせて造られた細長い建物には、ナンシーの街を見渡すさまざまなタイプの窓が設置されています。 ●エーロ・サーリネン、アレクサンダー・ジラード、ダン・カイリー「ミラー邸」 1957年建築 |
 |
 |
|
| すげぇ広大 | 豪邸ですな |
| アメリカの実業家、ミラー夫妻の依頼により、インディアナ州コロンバスにサーリネンが設計した豪奢な邸宅です。 内装にはジラードも参加し、造園家のカイリーが庭園を担当しました。 見事な調度とランドスケープを取り込んだ広大な庭を含め、きわめて豪奢な邸宅です。 ●菊竹清訓、菊竹紀枝「スカイハウス」 1958年建築 |
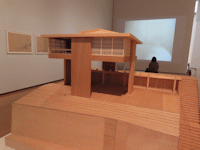 |
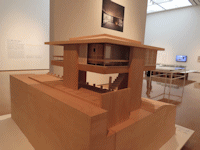 |
|
| スカイツリーのような家 | おー |
| 都市や建築も有機的に成長するとする建築運動「メタボリズム(新陳代謝)」を代表する菊竹夫婦の自邸です。 コンクリートの柱で持ち上げられた10×10mの居住空間の周囲に、「ムーブネット」と呼ばれる台所や浴室が、交換可能なものとして設置されました。 後に、カプセル状の子ども部屋のムーブネットも居住空間から1階のピロティに吊り下げられました。 ●ピエール・コーニッグ「ケース・スタディ・ハウス #22」 1960年建築 こちらも撮れる資料なし。 アメリカの建築雑誌『アーツ・アンド・アーキテクチュア』が企画した実験住宅プログラム「ケース・スタディ・ハウス」のひとつで、スタール邸とも呼ばれます。 ロサンゼルスを一望する天井までのガラス壁で囲まれた建物は、映画や雑誌など数々のメディアに登場しました。 ●ルイス・カーン「フィッシャー邸」 1967年建築 |
 |
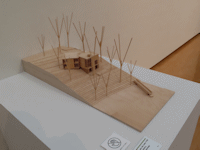 |
|
| おーカットモデルだ | 全景模型 |
| アメリカのフィラデルフィア郊外の自然豊かな場所に建つ、キューブ状のふたつの建物を、片方45度ずらして接続している邸宅です。 暖炉の脇にあるリビングの窓辺には、美しい景観を切り取るガラス窓や風を取り込む開閉窓、人が佇めるベンチなど、さまざまな用途が組み合わされています。 フィッシャー邸の窓辺の実物大模型もありました。 ●フランク・ゲーリー「フランク&ベルタ・ゲーリー邸」 1978年建築 |
 |
||
| なんかすごい |
| アメリカのカリフォルニア州の、ありふれた建売の住宅家の壁や天井をはずしたり、新しい材料を つけ足したりして、独自に拡張したいつまでも完成しない家としてつくられました。 使われている建材もまた、波型鉄板やチェーンリンクフェンス、既成の木材など、規格化された量産品です。 以上です。 結構楽しめましたねー。 |
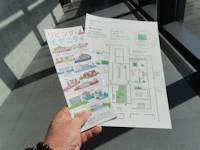 |
||
| 図録は今回は買わない |
| では帰りますか。 |
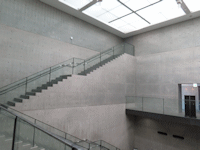 |
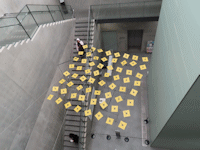 |
|
| 内部の吹き抜け | 別の展覧会の作品 |
| 地下駐車場へ。 |
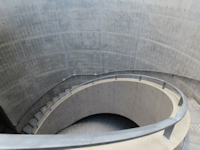 |
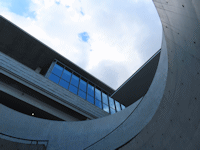 |
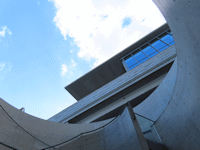 |
| 階段 | 上を観る | 青空ならなぁ |
| 駐車場から地上に出て北上。 神戸製鋼本社から一旦停止も確認もせず飛び出してきた車に危うく当てられそうになりながら日出脇浜線からR2へ。 R43を芦屋か西宮あたりまで走って行こうかと思いましたが、先ほど突っ込んできた車もR43方面に行こうとしていたので、気分悪いんでR2を走って行くことにしました。 |
 |
||
| 嫌な奴とは走らないでおこう |
| 「神戸の花火景品玩具卸売問屋クリス」ってのがあります。 一般でも購入できるようですね。 |
 |
||
| 冬でも商売になるのかな |
| 神戸市灘区にライダーズカフェ「PASSING」がありましたが、神戸市須磨区に移転してもその形跡は残ったままですね。 |
 |
||
| 「PASSING」跡 |
| 御影公会堂の前を通ります。 御影クラッセはすぐ近くなので、昼食は御影公会堂のオムライスでもよかったなぁ。 |
 |
||
| 御影公会堂 |
| 住吉川のところで、神戸新交通六甲アイランド線(六甲ライナー)が通過していきました。 |
 |
||
| 緑の車両 |
| 車両、あんなにかっこよかったかなぁ。と帰宅後調べると、これまでの1000系が、2018年から3000系に置き換わったらしいですね。 最後に六甲ライナー乗ったのって、多分、10年以上前だもんなぁ。 今のはフェラーリ・エンツォフェラーリやE6系・E7系新幹線、ヤンマートラクター YTシリーズなどを手掛けたデザイナー・奥山清行氏が全体監修を行ったそうです。 西宮でR171に入ります。 |
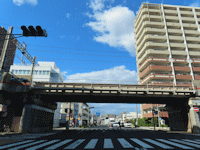 |
||
| R171に入りJRをくぐる |
| 阪急電車を越えていきます。 |
 |
||
| HondaCars兵庫・西宮店は今日は定休日 |
| 県道337号を北上します。 帰りに、親父のところに寄って行きました。 -15:45- 帰宅しました。 本日の走行距離 44km いろいろ買い物しましたね。 |
 |
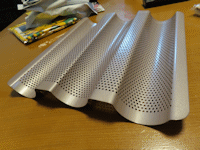 |
|
| パン作り器具とか | シェフメイド バゲットトレイ |
| 川上珈琲の豆は、エチオピア イルガチェフェ ナチュラル、・コロンビア ボンボ農協 ウォッシュド、・インドネシア マンデリンですよ。 |
 |
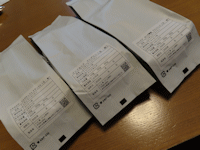 |
|
| 川上珈琲の豆 | 300gを3袋 |
| 沢の鶴では1本だけしか買わないでおこうと思いましたが、いろいろ買ってしまった。 |
 |
 |
 |
| 蔵限定澤之鶴純米原酒 | 古酒仕込み梅酒 | 灘の大吟醸酒けーき |
 |
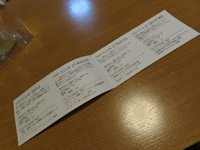 |
|
| ヴィンテージ古酒のみ比べセット | 1991 1997 2009 2014 |
| 単品の大瓶(といっても200ml)のラインナップとは違っていましたね。 とりあえずコーヒー生豆を100gずつローストしました。 |
 |
 |
|
| weroast出動 | いい感じ |
| 久しぶりに、お休みらしい過ごし方ができたかな。 灘五郷の御酒印帳蔵は、あとは西宮の4蔵と神戸酒心館だな。 西宮はまとめて電車で行ってみようか。 |
■ RockzGoodsRoom ■ Sitemap Copyright(C) RockzGoodsRoom All Rights Reserved.