 Rockzの愛車だったTMAX530と、バイクの話題の部屋です。
Rockzの愛車だったTMAX530と、バイクの話題の部屋です。※ここに掲載のカスタムを参考にされる場合はあくまでも個人の責任でお願いします。
 Rockzの愛車だったTMAX530と、バイクの話題の部屋です。
Rockzの愛車だったTMAX530と、バイクの話題の部屋です。
※ここに掲載のカスタムを参考にされる場合はあくまでも個人の責任でお願いします。
Last Update 2025/10/27
| 2001年にこれまでなかった「大型二輪免許で乗るスクーター」という、メガスクーターなるカテゴリで、YAMAHA TMAXが登場しました。 「オートマチックスポーツ」というカテゴリは二輪の世界に新しい風を吹き込んだと実感しています。 Honda Dio(50cc)、Honda SPADA(250cc)、Honda VFR400(NC30)(400cc)と乗り、その後一旦二輪から遠のいてHonda LEAD90に乗っていましたが、再びバイク熱に火かついて、大型バイクに乗ることになりました。 そして、2002年3月8日から15年間、2017年3月11日まで、4台のTMAXを乗り継いできました。 理由あって、現在二輪からは完全に降りていますが、また乗れる日が来ればいいなぁと思います。 とりあえず、過去に乗ったTMAXたちです。 |
YAMAHA TMAX530 (EBL-SJ12J) 2013.03.30〜2017.03.11 走行距離 37,949km 詳しくはこちら |
 Left View |
 with JADE |
YAMAHA TMAX (EBL-SJ08J) 2008.12.28〜2013.03.09 走行距離 45,109km 詳しくはこちら |
 Left View |
 with STREAM |
YAMAHA TMAX (BC-SJ04J) 2005.05.02〜2008.12.27 走行距離 76,142km 詳しくはこちら |
 Left View |
 with Edix |
YAMAHA TMAX (BC-SJ02J) 2002.03.08〜2005.04.16 走行距離 44,186km 詳しくはこちら |
 Left View |
 with ODYSSEY |
| 2年ぶりに、「Japan Mobility Show 2025」が31日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されます。 2023年からこの名称ですが、それまでは「東京モーターショー」と言っていました。 最後に行ったのは2017年のこと。 大阪モーターショーも最後に行ったのは2019年のこと。こちらは「Japan Mobility Show Kansai 2025」と名を変え今年は12月5日荒7日に開催されます。 最後に行った頃には、観ていてもワクワク感がなくなってきたなという感想でした。 EVとか省エネとか、環境配慮とか。 すべて正論なんでしょうね。でも、今でも自分の中ではエンジンの音とオイルの匂いが車であり、バイクなのですよね。 そこを覆すほどの面白さ、例えば走りなどあればまだワクワク感はあるのでしょうけど。 特に車は、EV、ハイブリットが進んで、あまりワクワクしません。 バイクも、バイク人口が減ってラインナップも少なくなってきたこともありますが、それだからこそ、YAMAHA NIKENやTRICITYは、どんな走りなのか乗ってみたくなるし、あと、小型のギア付きバイクなんかも面白そうと思ったりします。 そんなわけで、わざわざモビリティショー観に行こうという気が起きないんですよね。 今年の各メーカーは、どんなの出すのかなと何気に見ていたら、YAMAHAが面白いのを出しています。 TRICERA proto  前2+後1輪 前2+後1輪おー、なんか面白そうだぞ。 でもこれはバイクではないね。 3輪パッケージのフルオープンEVです。感性に訴える刺激的な旋回性能と、新感覚の操縦感を併せ持ち、意のままに操るための習熟プロセスさえ楽しい3輪手動操舵(3WS)の実走コンセプトモデルです。 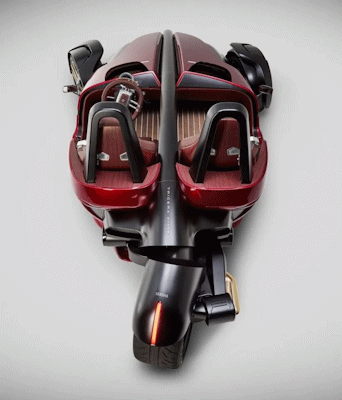 前後舵角がとれる 前後舵角がとれる前後輪操舵可能な車両の特徴である旋回応答性の高さと旋回時のドライバー感覚とのつながりに着目し、人間研究視点で最も FUN を感じる旋回制御とすることで、異次元の人機一体感を実現。 また、走行音をチューニング&調律するサウンドデバイス「αlive AD」を搭載し、操縦に没入するドライバーの高揚感を増幅します。 3輪構造を際立たせたセンターフレームによるアーチ型シルエットに加え、人間空間と機能空間の対置表現により独創的なデザインを実現したとのこと。  ちょっとノスタルジック ちょっとノスタルジックでもカッコイイですね。 日常乗りには厳しいですが、多分、乗ると楽しいんだろうなぁ。 |
| 電動キックボードは買おうとも乗ろうとも思いませんが面白いのが出ていました。 AVIOTってところが、マクロスなどのメカニカルデザインを手がけた河森正治氏デザインの「KB-S350」です。  これ これAVIOTはプレシードジャパンが展開するブランドで、2018年に誕生した日本発のオーディオブランドです。 日本人が最も心地良いと感じる周波数帯域に特化した音質「Japan Tuned」へのこだわりに加え、アニメキャラやアーティスト、VTuberなどとのコラボモデルも数多く手がけることで、幅広い支持層を得ているそうですよ。 そんなオーディオブランドが手掛けた電動キックボード。 2023年からは、オーディオ製品だけでなく、エレクトロニクスのトータルブランドとなるべく再スタートを切っていたことで今回の発売となったそうです。 ・・・・電動キックボードはエレクトロニクス製品なんだね。 16歳以上が運転免許不要で乗れる特定小型原付の電動キックボードで、国土交通省の車両保安基準審査制度「性能等確認制度」にて適合認定を受けています。 公道、歩道、どちらも走れますよ。 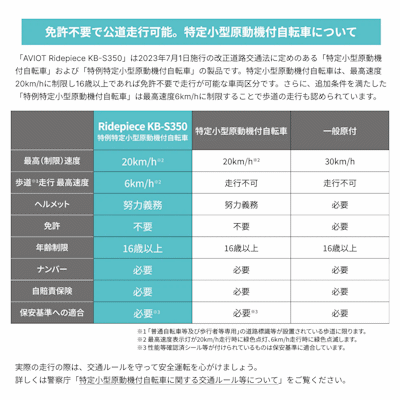 「特例」がつく特定小型 「特例」がつく特定小型ちなみに、公道モードと歩道モードを切り替えることで最高速度制御ができるようです。 諸元はというと・・・
175,000円かぁ。昔の原付くらいの値段ですね。 キービジュアルには「マクロスF」でキャラクターデザインなどを担当した江端里沙氏とのタッグで出来上がっています。  未来的 未来的売れそうですが、若者は日本ブランドより安価な中華を選ぶのかなぁ。 どうなんだろう。 |
| 鈴鹿8時間耐久ロードレースは、YMAHAの優勝を願っていたのですが、残念ながら2位フィニッシュとなりましたね。 ジョナサン・レイ選手に来てほしかったなぁ。 さて、8月25日、スーパーバイク世界選手権(WorldSBK)に参戦している、6度の王者である、そのジョナサン・レイ選手は、YAMAHAとの契約が切れる2025年シーズン限りで現役引退すると発表しました。  ジョナサン・レイ ジョナサン・レイ1987年、イギリス・北アイルランド生まれの38歳。 レースデビューは1997年。 ブリティッシュスーパーバイク選手権(BSB)、スーパースポーツ世界選手権(WorldSSP)を経て、2008年、スーパーバイク世界選手権にHondaからワイルドカード参戦して以来、最高峰クラスでの17年間のレースで459レースに出場。そのうち119回は優勝し、264回の表彰台、44回のポールポジション、104回のファステストラップを記録しています。 この記録は破られることはないだろうと言われているそうですね。 ちなみに、競技用ライセンスとは別に、34歳になるまで公道でのオートバイ運転免許は取得していなかったそうで、2021年8月に自動二輪免許を取得したそうです。 最高峰クラスにステップアップした2008年にはHonda参戦。この時は、WorldSBKはまだCBR600RRでしたね。  Honda CBR600RR Honda CBR600RR同年、高橋裕紀選手と組んでDream Honda Racing Team 33から鈴鹿8耐に初出場しますがリタイヤ。 2010年にもF.C.C.TSR Hondaから秋吉耕佑選手、高橋裕紀選手と組んで2度目の鈴鹿8耐参戦。3位入賞となります。 2012年にも再度F.C.C.TSR Hondaから秋吉耕佑選手、岡田忠之選手と組んで3度目の鈴鹿8耐参戦で見事優勝。  Honda CBR1000RR Honda CBR1000RRまた、同年には、ケーシー・ストーナー選手の代役としてスポット参戦で、MotoGPにも2戦出場していました。  Honda RC213V Honda RC213V2013年には三度目のF.C.C.TSR Hondaから清成龍一選手と組んで4度目の鈴鹿8耐参戦でしたがリタイヤ。 2014年もF.C.C.TSR Hondaから秋吉耕佑選手、ロレンツォ・ザネッティ選手と組んで5度目の鈴鹿8耐参戦でしたが40位と振るわず。 2015年にはカワサキ・レーシングチームに移籍すると初年度でチャンピオンを獲得。そこから6年連続で王座を獲得します。  Kawasaki ZX-10R Kawasaki ZX-10R2018年にはレオン・ハスラム選手、渡辺一馬選手と組んでKawasaki Team GREENから鈴鹿8耐に参戦。自身6度目の参戦は3位。 翌2019年はKawasaki Racing Team Suzuka 8Hからレオン・ハスラム選手、トプラク・ラズガットリオーグル選手と組んで7度目の鈴鹿8耐参戦で、Kawasaki26年ぶり、自身2度目の優勝となりました。  Kawasaki ZX-10RR Kawasaki ZX-10RR昨年より2年契約でYAMAHAに移籍し、Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Official Teamから参戦していましたが、怪我や不運などにより思うような成績を収めることができず、今年限りでの引退を決意したようですね。  YAMAHA YZF-R1 YAMAHA YZF-R1ひとつの時代のピリオドですね。 |
| いよいよ来週に迫った、鈴鹿8時間耐久ロードレース。 YAMAHAは、レース活動70周年ということで、2025年の鈴鹿8耐に2019年以来6年ぶりにファクトリー体制のゼッケン21番・YAMAHA RACING TEAMを復活させて参戦します。 そのカラーリングは1964年(昭和39年)のWGPで使用した伝統的なホワイト×レッドの日の丸カラーが採用され、デザインは1999年(平成11年)に鈴鹿8耐でYAMAHA RACING TEAMが走らせたYZF-R7にインスパイアされたものをリデザインした特別なものとなったのは先に書いた通りです。 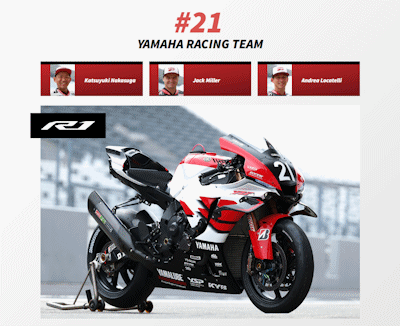 #21 YAMAHA RACING TEAM #21 YAMAHA RACING TEAMそして、2001年からFIM世界耐久選手権(EWC)に参戦するYAMAHAの耐久トップチームYART(YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM)も、今年も参戦。 正式にはYamalube YART Yamaha EWC Official Teamと言います。 2023年にはFIM世界耐久選手権の年間チャンピオンにもなっています。 カレル・ハニカ選手、マーヴィン・フリッツ選手、新加入のジェイソン・オハローラン選手の3人態勢で挑みます。 YARTのマシンは、チーム名からもわかるように、YAMAHAのエンジンオイル、Yamalubeのカラー、青を基調としたマシンです。 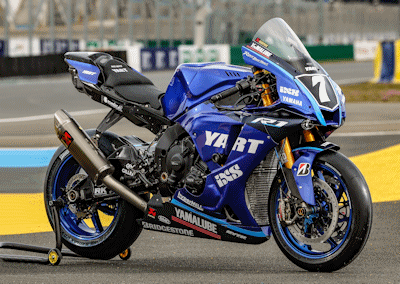 #7 2Yamalube YART Yamaha EWC Official Team 現在、EWCのシリーズランキングトップ。 このYARTのマシンも、鈴鹿8耐だけは70周年記念カラーで挑みます。 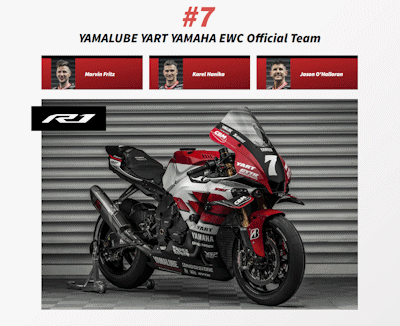 #7 YART #7 YARTどちらもYZR-M1ですね。 優勝目指してがんばってもらいたいです。 なお、テレビ放送は、BS12で11:00からやるようです。 |
■ RockzGoodsRoom ■ Sitemap Copyright(C) RockzGoodsRoom All Rights Reserved.